パット・メセニー × オーネット・コールマン『Song X』をもう一度聴く
1985年に登場した『Song X』は、ジャズ史の中で特異な立ち位置を占める作品である。パット・メセニーとオーネット・コールマンという、異なる美学を担った二人の巨人が共演したにも関わらず、当初の評価は必ずしも芳しいものではなかった。メセニーのファンからすれば「もっと構築されたサウンドが聴きたい」と感じ、オーネットのファンからは「もっと暴れてほしい」と思われた。その結果「どっちつかず」という印象だけが広まってしまった。
だが、この“中間的で落ち着かない場所”こそが、実は『Song X』が最も輝く地点だったのではないか。つまり本作を貫くのは、混ざらなさ=価値という、従来の異文化コラボレーションにはなかった美学である。
メセニーとオーネットの間に立ち上がる「混ざらなさ」
メセニーは80年代までに、浮遊感と透明度の高いサウンド、エフェクトを用いた空間性、そして緻密な構築美を特色として確立していた。一方、オーネットはハーモロディクスという“構造を前提にしない即興体系”をさらに押し進めていた。両者は「自由なジャズ」を志向すると言えば同じ方向に見えるが、実際には美学の根本が異なる。
メセニーは構築の人であり、オーネットは解体の人である。
その二人が同じ舞台に立ち、同時に演奏する――その結果、どちらかがどちらかを飲み込むことは起こらなかった。ギターはギターの地図、サックスはサックスの地図を持ち、それぞれが異なる重力を抱えながら並走する。
この“混ざらなさ”は、フリージャズの爆発でもなく、メセニー的統一美でもない。まさに両者の語法が隣り合うだけの状態から、奇妙で独自の空間が生まれているのである。
「混ざり合った成功例」ではなく「並置の成功例」――新しい角度から見える『Getz/Gilberto』
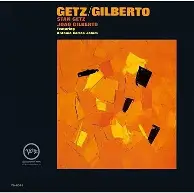
ここで鍵となるのが、『Getz/Gilberto』(1964)を別の角度から聴き直してみる、という試みである。長くこの名盤は「ボサノヴァとジャズの完璧な融合」と受け取られてきた。しかし視点を変えて耳を澄ませば、音楽の核はむしろ “混ざらずに並んでいること” に宿っているように聞こえてくる。
ゲッツのサックスはアメリカ的クールネスを保ったまま流れ、ジルベルトのギターと歌はブラジルのリズム文法を一歩も動かさない。互いが相手に合わせようとせず、それぞれの流れを保ったまま隣り合う。その結果、異なる文法が溶け合わずに大理石のような縞模様をつくり、むしろその「ズレ」こそが美として露わになる。
そう考えると、『Getz/Gilberto』は異文化音楽の“融合成功例”ではなく、異文化が混ざらず併存することの魅力を早くから提示していた作品として位置づけられる。そして、この「混ざらないままの共存」を、よりラディカルな形で押し出したのが『Song X』だと捉えることも可能になる。
異文化を「取り込む」タイプの混合 ― 『Sketches of Spain』が示す別のモデル

対照的なのは、マイルス・デイヴィス『Sketches of Spain』である。この作品はしばしば異文化融合の名盤とされるが、一方で“スペイン音楽を素材として加工する”という構図を持つ。つまり、異文化を自国のフレームに取り込み、整形し、美として再配置するという方法論である。
このモデルは、ある種の同化型・吸収型の混合であり、外来文化を「素材化」することで作品に統合していく。美しく整った結果が得られる一方、文化間の非対称性や、政治的な権力関係をいかに扱うかという課題も孕む。
この混ざり方は、並置的で混ざらない構造を価値とする“マーブリングの美学”とは根本的に異なる。『Sketches of Spain』は異文化を「飲み込む」アルバムであり、『Getz/Gilberto』や『Song X』は異文化が「並び立つ」アルバムなのである。
『Song X』は並置が極限まで露出したアルバムである
『Song X』の核心は、まさに“混ざらなさの露出”である。
メセニーはメセニー的な構築をやめず、オーネットはオーネット的な線の自由を手放さない。
それでも互いに無関心でも敵対でもなく、ただ互いを飲み込まないまま同じフィールドに立つ。この“横に並びながら共存する”構造は、ゲッツとジルベルトの並置構造をより抽象化・脱調性化した姿とも言える。
それは決して融合でも対話でもなく、むしろ平行線が続きながら、交わらない線同士が時折ぶつかり、離れ、また近づくという動きである。その運動そのものが音楽になっている。
1985年当時のリスナーは、この“混ざらなさの動き”に戸惑った。しかし現代の耳で聴くと、まさにそこにこそ創造のリアルがあると感じられる。文化はしばしば混ざらず、ただ隣り合うだけである。その隣り合いの摩擦や空白こそ、現代的で複雑な価値を生む。
混ざらないことの勇気 ― 『Song X』が切り開いた未来
異文化が出会ったとき、人はしばしば「うまく混ざり合うこと」を成功の尺度としてしまう。音楽においても、異ジャンルの共演が評価される場面では、調和・融合・一体化といった言葉が中心に置かれ、まるで文化同士が自然に溶け合うことが唯一の正解かのように扱われてきた。しかし、実際の文化の動きはもっと複雑で、もっと不安定で、もっと居心地の悪いものだ。むしろ溶けず、混ざらず、ただ隣り合いながら進むことの方が多い。
『Song X』が提示したのは、その“居心地の悪さ”をこそ美学として引き受ける姿勢である。

メセニーとオーネットは、互いに寄り添わなかった。だが、それは拒絶ではない。どちらも自分の言語を手放さなかったからこそ、両者は対等でいられた。つまり、本作が成し遂げたのは「相手の語法を吸収して自分の一部にする」ことではなく、「異なる語法がそのまま共存してよい」という状態を、音楽として成り立たせた点にある。
その結果として生まれた摩擦、空白、ねじれ、ぎこちなさ。それらは従来のジャズが“整理してしまおう”と避けてきた領域だった。しかし現代的な耳で聴くと、その摩擦こそが最も豊かな部分になっている。
ここで重要なのは、混ざらないことは妥協ではなく、むしろ強い意志の表明であるという点だ。メセニーの構築美と、オーネットのハーモロディクスは、本質的に異なる方向を向いている。どちらかが譲歩した瞬間に、作品は別の姿――もっと分かりやすく、もっと統合的で、もっと市場に理解されやすいもの――になってしまっただろう。それはある種の“調停”であり、“商品としてのまとめ方”であり、“融合のふりをした弱い妥協”になる危険があった。
しかし『Song X』はその安易なつじつま合わせを徹底して避けた。ここにこの作品の硬質な誠実さがある。
絵画で言えば、同じキャンバスにまったく異なる筆致や色面が置かれ、混ざらず、独立した重力を保ったまま並存しているマーブリングに近い。文学で言えば、異なる言語体系が翻訳されずに並列されるテクストの多言語性。建築で言えば、複数の文化的レイヤーが同じ都市空間に積層し、決して一つのスタイルに均質化されない“複合的景観”に通じる。
『Song X』はジャズの中で、このような“複数性がそのまま露出した状態”を実践している。つまり、文化はそもそも一つにまとまらないものであり、まとまらなくてよい――という価値観を、音として提示したのである。
この姿勢がどれほど困難で、どれほど孤独を伴う挑戦だったかは、当時の受容の冷たさが示している。1985年のリスナーにとって、この並置的な音響は「未完成」「粗暴」「中途半端」と映ったかもしれない。しかし、それはむしろ本作が従来の評価枠組みの外側へ踏み出した証拠である。
従来の尺度では測れないものは、しばしば「曖昧」「曖昧さすぎる」と見なされる。しかし、それこそが本作の意図であり価値だったのだ。
今日、文化研究やポストコロニアル理論、アートの新潮流では、混ざらない並置、境界の曖昧さ、越境の摩擦こそが創造の源泉として再評価されている。『Song X』は、この価値観の到来を30年以上も先取りしていた。融合を求められる状況で、あえて混ざらないまま立ち続けるという勇気。これは音楽的にも思想的にも、極めて現代的な態度である。
いま私たちがこのアルバムに改めて向き合うべき理由はまさにそこにある。異文化の共存は、決してひとつにまとまることではない。むしろ、異なるまま同じ場に立ち続けることの緊張と美しさ――その価値を見抜いた作品として、『Song X』はいまこそ再び輝くのである。

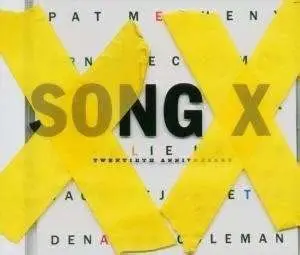


コメント