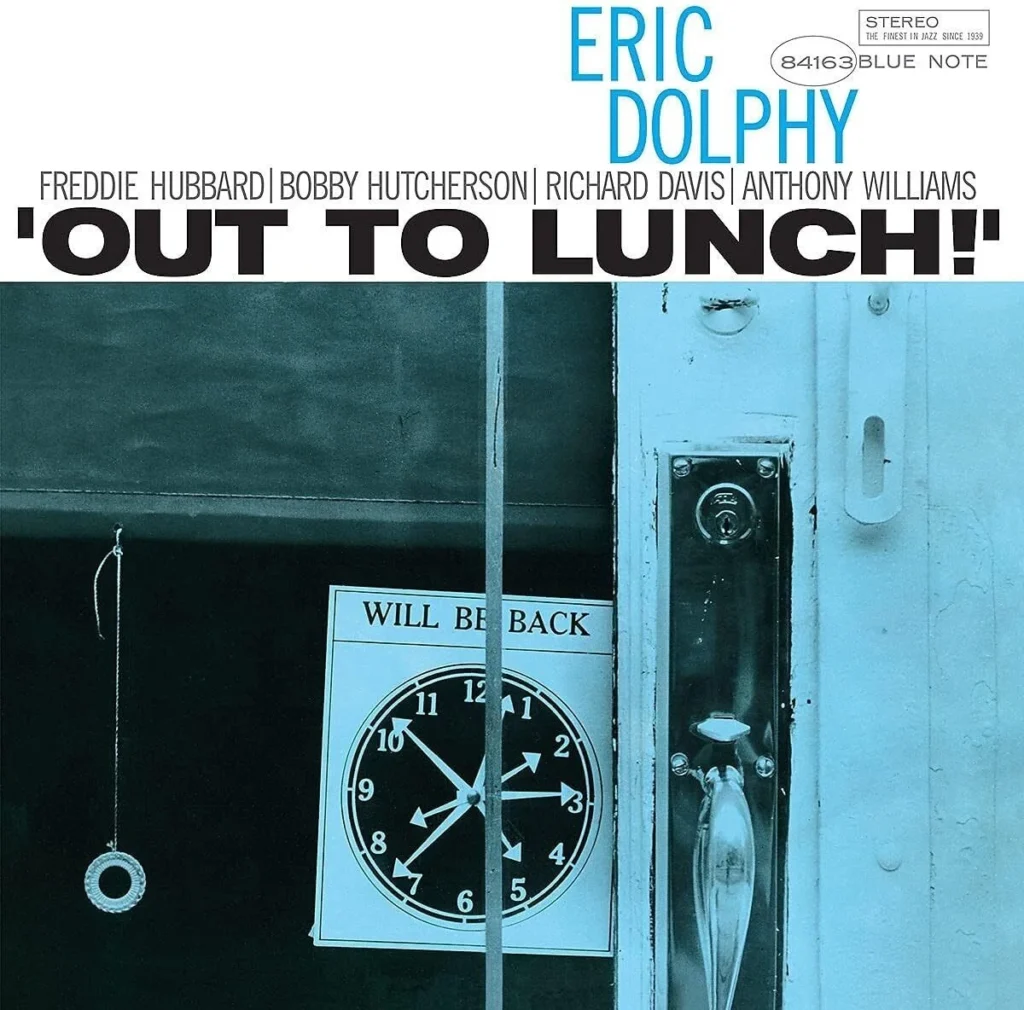
エリック・ドルフィー『アウト・トゥ・ランチ!』
エリック・ドルフィーの『Out to Lunch!』(1964年)は、フリー・ジャズの代表作として語られることが多いが、その音楽的実態は、一般に想定される「自由即興」や「無調的混沌」とは明らかに異なる。むしろ本作が示しているのは、高度に構築された知性と、感覚的な熱量が同時に存在する、きわめて特異なモダンの姿である。そこでは抽象化が行われているにもかかわらず、音楽は決して冷たくならない。『Out to Lunch!』は、完成へと向かう近代的モダニズムの道筋から逸れつつ、別の方向へと分岐した「オルタナティヴ・モダン」の一つの到達点と考えることができる。
ドルフィーは、幼少期から体系的な音楽教育を受け、近代ヨーロッパ音楽の語法 ― 印象派的和声、対位法、さらには十二音技法的思考 ― を十分に理解していた演奏家である。しかし彼は、それらを理論として提示することも、体系として完成させることもしなかった。むしろ、膨大な音楽的知識を「引き出し」として内部に蓄え、それらを状況に応じて瞬時に選び取り、組み替えることのできる情報空間を自身の内側に形成していた。そのためドルフィーの演奏には、吹き始めから一気にエンジンをふかすような急発進性がある。探りを入れながら進行するソニーロリンズ的な即興とは異なり、すでに複数の可能性が同時に見えている状態から、演奏が始まっているのである。

この性質は、ファイヴ・スポットでのライヴ音源と『Out to Lunch!』を比較すると、より鮮明になる。ライヴにおけるドルフィーは、身体的反応と生成のスリルを前面に押し出し、音楽がその場で生まれていく感覚を強く残している。一方『Out to Lunch!』では、音楽は即興でありながら、あらかじめ設計された構造の内部で展開される。生成の快楽よりも、「解決しない状態を維持すること」そのものが主題化されているのである。
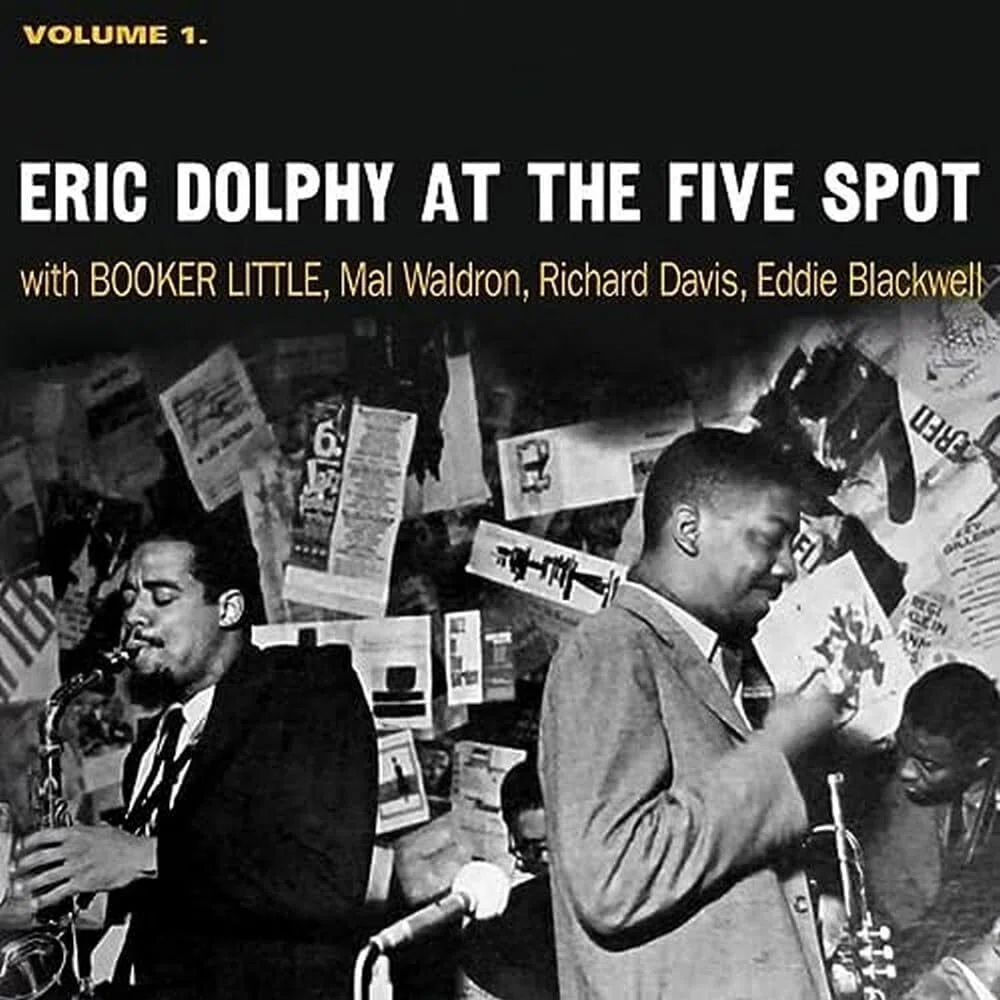
このアルバムに特有の宙づり感は、演奏者たちの役割分担によって精密に支えられている。フレディ・ハバードは、ハードバップ以降のモダン・トランペットの語彙を完全に身体化した存在であり、ここでは感情的な叫びではなく、極めてテクニカルで整ったラインを提示する。その結果、音楽は「いつでも着地できたはずの可能性」を常に示されながら、実際にはどこにも降り立たない状態に置かれる。ハバードの明晰さは、安定をもたらすのではなく、むしろ構造の歪みを際立たせる装置として機能している。

ボビー・ハッチャーソンのヴィブラフォンもまた、和声楽器でありながら、音楽の床を作らない。彼の響きは空間の色温度を変え、雰囲気を濃密にするが、調性的な帰結点を与えない。和音は鳴らされるが、そこに留まることは許されない。これは和声を曖昧にしているのではなく、和声そのものを宙づりにするという、きわめて自覚的な選択である。

トニー・ウィリアムスのドラムは、拍を壊しているのではなく、拍が存在することを常に示しながら、それを踏ませない。時間は進行しているが、方向性を失っている。このように『Out to Lunch!』では、全員が高度な支えの能力を持ちながら、あえて支えないという倫理を共有している。そのため、抽象化が進んでも音楽は冷却されず、緊張と熱量を保ったまま持続する。

この宙づりのモダンは、同時代のコルトレーン『Giant Steps』に代表されるモダン化とは明確に異なる。『Giant Steps』が、和声的問題を提示し、それを技術によって解決する近代合理主義の完成形であったとすれば、『Out to Lunch!』は、解決可能な状況にありながら、あえて解かないことを選ぶ音楽である。進歩や到達を目的とせず、複数の可能性を同時に開いたまま保持する態度が、ここにはある。
この点で『Out to Lunch!』は、マイルス・デイヴィス『Nefertiti』と鏡像関係にある。『Nefertiti』が、表層を固定し、内部で運動を過剰化することで宙づりを生み出したのに対し、『Out to Lunch!』は、過剰な運動そのものによって着地不能の状態を作り出す。操作は正反対でありながら、両者は「冷えない抽象」という同一の地点に到達している。
このように見たとき、『Out to Lunch!』はフリー・ジャズへの過渡期でも、逸脱的な実験作でもない。それは、モダンであることを完成させないという、もう一つのモダンの姿を提示した作品である。異なる理論、異なる文化的背景、異なる音楽語彙が、溶け合うことなく同一平面上に並置される。その状態を肯定する態度は、カツカレーカルチャリズムが示す混成と共存の思想とも深く共鳴している。
『Out to Lunch!』が今日なお強い現代性を持つのは、音楽が単一の正解へと収束しない世界を、すでに先取りしていたからである。感受されるあらゆる音が観測可能であり、その観測の仕方そのものが音楽になる。ドルフィーの音楽は、そのような多世界的な感覚を、60年代という時代においてすでに実装していた。だからこそ、この作品は半世紀以上を経た現在においても、聴かれるたびに新鮮さを失わないのである。
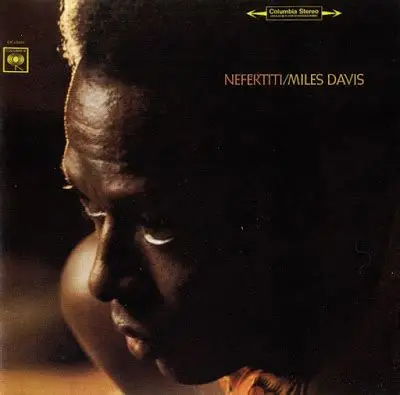
マイルス・デイヴィス『ネフェルティティ』
マイルス・デイヴィスの『Nefertiti』(1967年)は、しばしば〈第二期黄金クインテットの完成形〉、あるいは〈ポスト・バップからフリーへの橋渡し〉として語られてきた。しかし本作の核心は、スタイルの移行点にあるのではなく、モダン・ジャズが内包してきた「進行」「発展」「解決」という時間概念そのものを、内部から停止させる点にある。
『Nefertiti』において最も象徴的なのは、表題曲をはじめとする複数曲で、管楽器がテーマを執拗に反復し、通常期待されるソロ展開が起こらないことである。メロディは提示され、しかし展開されない。音楽は始まっているのに、前に進まない。この構造は、聴き手の側に強い違和感と緊張を生むが、それは混乱や破壊によるものではない。むしろ、すべてが高度に制御された状態で起こる、意図的な停止である。
この「停止」は、音楽が動いていないことを意味しない。むしろ逆に、リズム・セクション、とりわけトニー・ウィリアムスのドラムは、かつてないほど流動的で、密度が高く、暴力的ですらある。拍は刻まれ、しかし踏みしめることができない。時間は流れ続けているが、方向性を持たない。ここで起きているのは、表層の固定と深層の過剰運動という、二重構造である。
この二重構造こそが、『Nefertiti』に特有の宙づり感を生み出している。通常、ジャズにおける即興ソロは、時間を前進させる装置として機能する。テーマから逸脱し、緊張を高め、解決へと導く。しかし『Nefertiti』では、その役割が意図的に奪われる。ソロが抑制されることで、音楽は「どこへ向かっているのか」という問いを、宙に浮かせたまま持続させる。

この態度は、同時代のコルトレーン的モダン化 ― たとえば『Giant Steps』に象徴される和声的加速と問題解決型の即興 ― とは明確に異なる。『Giant Steps』が、より複雑な問題を提示し、それを技術によって解決する近代合理主義の音楽であったとすれば、『Nefertiti』は、解決可能な状況にありながら、あえて解決を延期する音楽である。
この「解かない」という選択は、技術不足の結果ではない。マイルス、ショーター、ハンコック、カーター、ウィリアムスというメンバーは、当時考えうる最高水準の能力を備えていた。その上で、彼らは進行しないことを選ぶ。これは、モダン・ジャズが内包してきた進歩史観に対する、きわめて静かな、しかし決定的な批評である。

『Nefertiti』をエリック・ドルフィー『Out to Lunch!』と対比すると、その位置はさらに明確になる。『Out to Lunch!』が、過剰な運動と情報密度によって着地不能の状態を作り出していたのに対し、『Nefertiti』は、表層を固定することで運動を内側に折り畳む。両者は正反対の操作を行いながら、同じ地点 ― すなわち「冷えない抽象」「未解決のモダン」― に到達している。
重要なのは、『Nefertiti』がフリー・ジャズへ向かう途中段階ではないという点である。この作品は、破壊の前夜ではなく、完成の内部で停止するという、別種のラディカリズムを示している。自由になるために壊すのではなく、完成しすぎた構造の中で、あえて動かない。
この意味で『Nefertiti』は、ポストモダン以前に存在した、オルタナティヴなモダンの一形態と捉えることができる。それは多様性や混成を祝福する態度というよりも、単一の正解へと向かう力そのものを弱める倫理である。 現代の音楽環境は、複数の理論、複数の価値基準が併存し、どこにも最終的な着地点が存在しない状態にある。その意味で、『Nefertiti』の示した「静止による宙づり」は、いまなお強い現代性を持つ。動かないことで問いを持続させる。この作品は、ジャズ史の中の一枚の名盤である以上に、思考の態度として聴き継がれるべき音楽なのである。





コメント