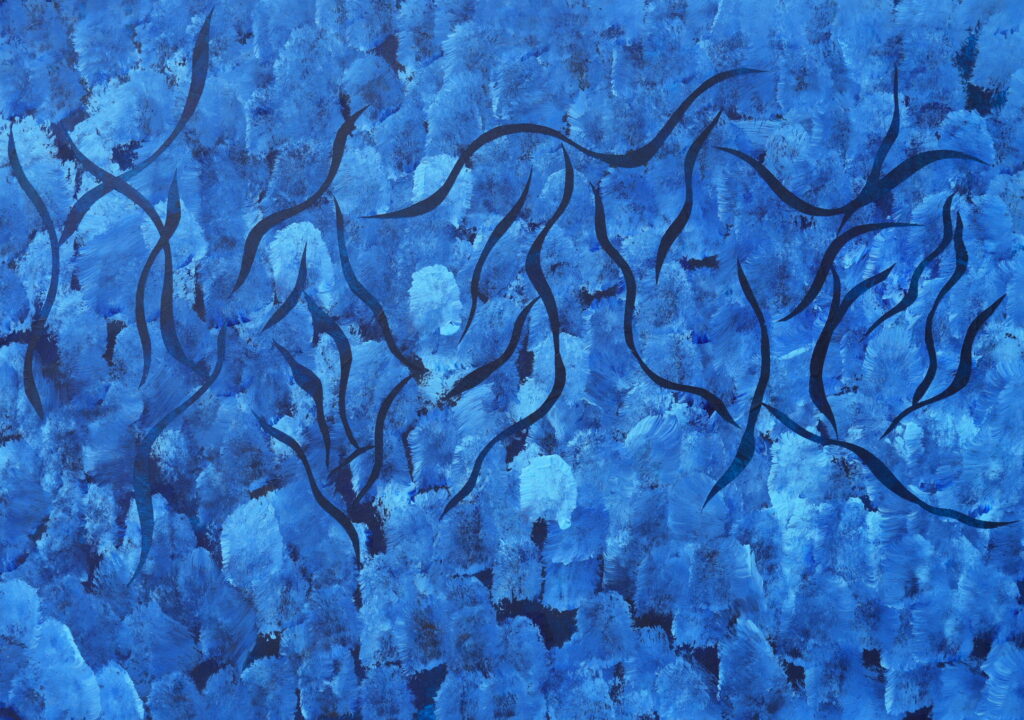
イメージが世界を代表しなくなった時代
現代において、イメージはもはや希少なものではない。スマートフォンやSNS、生成AIの普及によって、視覚像は過剰なまでに生成・流通し、私たちは意識する間もなくそれらを消費し続けている。かつて絵画が担っていた「世界を像として提示する」という役割は、情報量と即時性において他のメディアに完全に凌駕されている。
重要なのは、イメージが増えたことそれ自体ではない。問題の核心は、イメージがもはや「世界の代表」ではなくなった点にある。どのイメージも暫定的で、どの像も他の像によって容易に上書きされる。世界は一つであり、それをどう描くかという問いは、すでに成立しない。現代の視覚環境は、無数の可能世界が並列に存在し、観測されることでのみ一時的に立ち上がる、多世界的な構造を帯びている。
観測点としての主体とマイワールド
この多世界的環境において、主体のあり方もまた大きく変化している。主体はもはや、統一された内面や一貫した世界観を持つ存在として前提されない。むしろ主体は、どのイメージを選択し、どの視覚的流れに身を置くかという観測点の集合として存在する。
人は無数のイメージの中から、意識的・無意識的に選択を行う。その選択は思想や信念によるというよりも、安心感、不快の回避、認知的負荷の低さといった必要性によって駆動されている。その結果として形成されるのが、個人化された視覚的現実、すなわちマイワールドである。
このマイワールドが他者と部分的に重なり合うとき、コミュニティが生まれる。そこでは理念や価値観が共有されるというより、視覚的・感情的な最適化のパターンが近似している。その近似領域が「リアル」として感知されるが、それは恒常的な現実ではなく、同期が保たれているあいだだけ成立する、きわめて脆弱なリアルである。
ヴィジョンの変容 ― 世界像から観測の痕跡へ
このような状況において、絵画におけるヴィジョンの意味は決定的に変容している。かつてヴィジョンとは、画家固有の世界観であり、世界がこのように見えてしまうという不可避性を伴った像であった。ホッパー(世界は見えているが、意味が欠落している状態)やベーコン(意味や主体が、画面の暴力によって壊される状態)、あるいはフィッシュル(日常的イメージが、倫理や物語に回収されきらない状態)の絵画には、個人的でありながら逃れがたい視覚の強度があり、それが作品を支えていた。
しかし現在、そうした統一的なヴィジョンを成立させていた条件は崩れている。世界は一つではなく、主体もまた一枚岩ではない。どの像も、別の世界線の存在によって相対化されてしまう。そのため、世界を代表する像を掲げることは、容易にフィクションとして露呈してしまう。
それでもなお、絵画におけるヴィジョンが消滅したわけではない。むしろヴィジョンは、その性質を変えて存続している。現代のヴィジョンとは、世界を統合する像ではなく、世界が分岐し続けていることを、ある一点からしか見られないという自覚そのものである。全体像を把握できないこと、観測が偏っていること、その偏りから逃れられないこと。それらを引き受ける態度が、現在のヴィジョンの核となる。
この意味で、絵画はもはや「世界像」を提示するメディアではない。絵画が担うのは、無数の可能世界の中で、なぜかこの世界線を通ってしまったという痕跡を固定してしまう行為である。そこには常に、別の像がありえたという否定形が含まれている。絵画のヴィジョンは、選択の結果としての不完全さ、取りこぼし、偏りを沈黙のまま内包することで成立する。
メタ化する視覚と没入の危機
現代の視覚環境は、必然的にメタ化を促す。視覚や造形言語は自己言及的になり、見ることの条件そのものが露出してしまう。構図や様式、引用や参照は、即座に文脈化され、説明可能なものとして回収される。
このメタ化は、批評性や距離をもたらす一方で、制作にとっては深刻な危機を孕む。制作は本来、時間の流れが歪み、判断が身体化する没入状態を通過しなければ、作者自身のリアルに触れることができないからである。制作中にメタ認知が前景化すると、判断は遅れ、画面は意味に先回りされ、時間の連続性が断ち切られる。
重要なのは、メタを否定することではない。むしろメタは、制作の方向性を定める段階や、完成後の振り返りにおいて不可欠である。ただし制作の最中においては、没入が守られなければならない。この時間的分離こそが、現在考えうる最も現実的な制作倫理である。
メタに回収されない画面の条件
では、メタに回収されない画面とはどのようなものか。それはまず、説明に先回りされない画面である。どの文脈に属するのか、なぜこの表現なのかが一瞬で理解できてしまう画面は、容易にメタ的把握の対象となる。逆に、意味が後から追いかけてくる画面では、鑑賞者は一度立ち止まらざるを得ない。
そのような画面には、判断の痕跡が未整理のまま残っていることが多い。なぜその色なのか、なぜその形が残っているのか、作者自身も完全には説明できない部分がある。しかし、その部分を消すと画面が死んでしまう。この「消せないが説明できない」領域こそが、没入の時間が造形の中に沈殿した痕跡である。
また、メタに回収されにくい画面では、観測距離が安定しない。近づくと別の絵になり、引くと関係が崩れる。細部が全体に従属せず、全体も細部を統御しきれない。この不安定さは、鑑賞者の観測点を固定させず、意味化を遅延させる。
時間の扱いも重要である。説明可能な画面では、制作時間が一本の線として想像できる。しかしメタに回収されない画面では、後戻りや中断、異なる時間の層が重なっているように感じられる。鑑賞者は、いつ何が起きたのかを特定できず、その結果として物語化が宙吊りになる。
さらに意外なことに、こうした画面では強度の弱い部分、迷いや力の抜けた部分が、全体のバランスを支えている場合が多い。一番うまく描けている部分や、一番派手な部分が中心になると、意図の所在は明確になり、メタは入り込みやすくなる。中心が曖昧であること、重心がずれていることが、回収への抵抗となる。
決定的なのは、作者自身がその画面を完全には位置づけられないという点である。何と呼べばいいかわからないが、壊す気にもなれない。その状態で手放される画面は、作者のメタ理解よりも先に進んでしまった結果として存在している。メタに回収されない画面とは、没入の時間が整理されきらないまま残ってしまった画面なのである。
不完全な観測を引き受けるということ
氾濫するイメージの時代において、絵画が担えるヴィジョンとは、世界を統一する像ではない。多世界的な視覚環境のなかで、ある一点に落ちてしまった不完全な観測を引き受けること。その没入の時間が、説明や意味に回収されきらないかたちで画面に残っているとき、絵画はメタを一時的に停止させ、見ることそのものを揺さぶる力を持ち続ける。




コメント