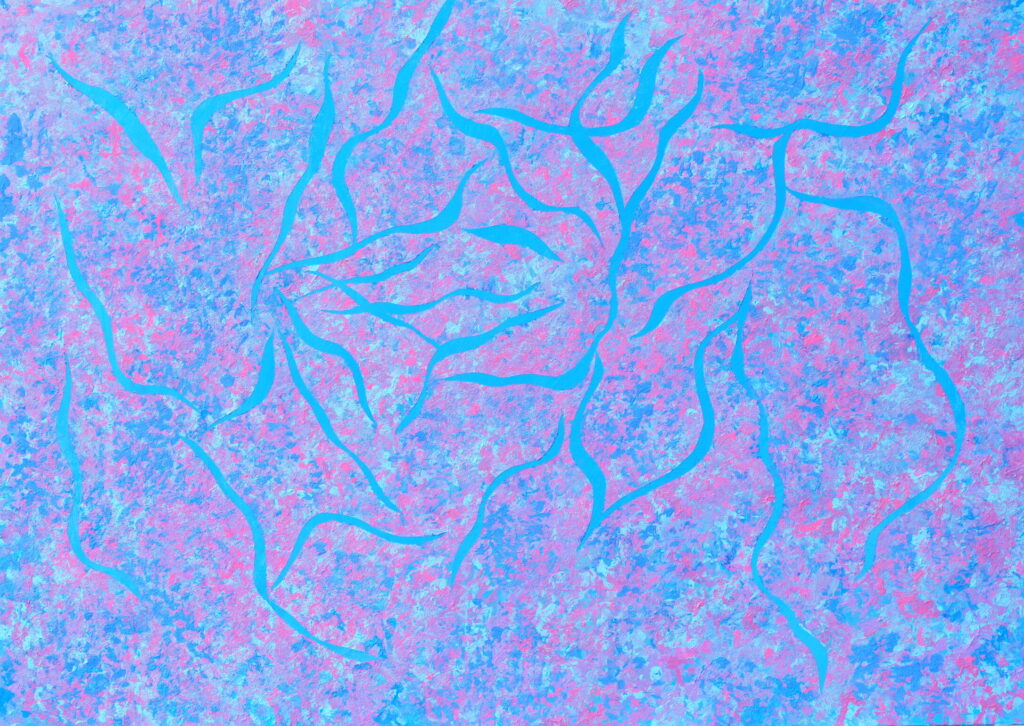
本稿で扱う「カツカレーカルチャリズム」については、これまでにも断片的に触れ、別の機会に概要を説明してきた。そこでは主に、多文化性や混成の感覚を比喩的に示すことに重きが置かれていたが、その全体像や内部構造を十分に言語化できていたとは言い難い。
ここでは改めて、カツカレーカルチャリズムを構成する複数の軸を整理しつつ、それが単なる文化比喩ではなく、アートや社会の関係を捉え直すための思考の枠組みとしてどのように機能しうるのかを、やや踏み込んで考えてみたい。
これは完成された理論の提示ではなく、むしろ味わいながら更新され続ける思考のレシピのようなものである。
多文化性 ― 溶けない混成としてのマーブリング
カツカレーカルチャリズムの第一軸である「多文化性」は、文化の差異を溶かして均質化する多文化主義とは異なる。ここで想定されているのは、複数の文化が同時に在り、それぞれの由来や質感を保ったまま並存する状態である。それはマーブリング(marbling)― それぞれの色や質感、由来を保ったまま、互いを縁取るように並存する混成状態である。
マーブリングの感覚において、異文化との出会いは対立や摩擦の前に、まず「味」として立ち上がる。異なる言語、信仰、身体感覚、生活習慣が交差することで、単一文化の内部では決して生成されない複合的な感触が生まれる。
アートにおいて、異素材や異技法、異なる文脈がぶつかり合い、偶然の化学反応によって予期せぬ魅力を生むように、文化の混成もまた創造的である。
カツカレーカルチャリズムは、この「出会いが新しい質を生む瞬間」を祝福する思想である。そこでは純粋性は価値の基準ではなく、むしろ混成のあり方こそが問われる。
境界横断性 ― 共生のための審美学
第二軸「境界横断性」は、国境を越えることやグローバル化のみを意味する言葉ではない。それは、文化、世代、ジェンダー、信仰、感性といった複数の境界を行き来しながらも、自身の輪郭を失わずに他者と関係を結ぶ柔軟さを指す。
ここで重要なのは、境界を消去することではない。むしろ、境界が可視化されたまま共存することである。
カツカレーの皿を思い浮かべればよい。ルーの辛味、カツの香ばしさ、ライスの白さは、完全に混ざり合うことなく、それぞれが独立したまま同じ経験を構成している。主役と脇役は存在せず、序列もない。
この構造は、社会における多文化共生の別の像を提示する。文化が交わるとき、私たちは往々にして「理解」や「統合」を求める。しかし理解とは、他者を自分の言語へ翻訳する行為でもある。
カツカレーカルチャリズムが重視するのは、理解に先立つ「味わい」である。翻訳を急がず、差異を差異のまま受け取り、咀嚼する。その態度が、次の軸である〈余剰性〉を要請する。
余剰性 ― ズレと過剰が関係を生かす
第三の軸「余剰性」は、異文化性と境界横断性を理念に終わらせず、生きた関係として持続させるための条件である。
文化や他者が交わるとき、すべてが理解され、整理され、意味づけられる必要はない。むしろ、理解しきれない部分、説明不能なズレ、過剰な要素が残されていることこそが、関係を閉じさせない。
余剰とは無駄や失敗ではなく、管理や最適化からこぼれ落ちた部分であり、そこに想像力が入り込む余地が生まれる。
アートにおいても同様である。作品の魅力は、完成度や論理的一貫性よりも、違和感やノイズ、過剰な色彩、沈黙や遅さといった「回収されない部分」に宿ることが多い。
余剰性とは、意味を確定させないことの力であり、他者や作品を完全に所有しないための倫理でもある。
異文化や他者を「わかったつもり」にならず、不可解さを不可解なまま置いておく。その余白があるからこそ、共存は支配や同化ではなく、生成のプロセスとして続いていく。
そして、この余剰があるからこそ、関係はやがて「美味しさ」という感覚へと転化する。美味しさとは、常に予定調和をはみ出したところで立ち上がるからである。
美味しさ(映え)の幸福 ― ケアとしての経験
第四軸「美味しさ(映え)の幸せ」は、前三軸がもたらす状態の経験的な結実である。
ここで言う美味しさは、単なる快楽や消費的満足ではない。異なる文化、価値観、感情が交わり、余剰を含んだまま成立する関係的な滋養を指す。
アートは世界を味わうための食卓であり、作品は皿の上のカツカレー、作家は料理人、鑑賞者は共に食べる客である。甘味も苦味も含めて混ざり合うことで、幸福という複雑な味が立ち上がる。
ここにアートのケアの機能がある。癒しではなく、関係を続けるための栄養としてのケアである。
「映え」とは、単なる視覚的魅力ではない。それは光を受け、他者に差し出される状態 ― すなわち、共有の回路が開かれていることを意味する。
作品が映えるとき、それは自己完結的な純粋性を脱し、社会的に機能している。美味しさの幸福とは、余剰を抱えたまま他者に差し出せる状態そのものなのである。
エピローグ 混ざる勇気の美学
文化は本来、混ざることでしか更新されない。閉じた純粋性を追い求める世界では、文化は硬直し、生命力を失う。異なるもの同士が偶然交わり、摩擦し、時に衝突しながら新しい形を生み出すとき、そこに創造の核心が宿る。
生成AIやアルゴリズムが創作に関わる現代において重要なのは、正確に作る力ではなく、何を見て、どう結び、どう味わうかという想像力の柔軟さである。技術はアートを置き換えるのではなく、新しい調理法を差し出す。
カツカレーカルチャリズムは、文化を閉じた体系としてではなく、常に開かれ、交わり、再構成されるプロセスとして捉えるための思考法である。混成は折衷ではない。それは異なるもののあいだに希望を見出す想像行為だ。
皿の上でカツとカレーが互いを尊重しながら共存する ―
その一瞬の「思いがけない美味しさ」の中に、未来のアートと社会の可能性は、確かに立ち上がっている。




コメント