仮面としての声、編集としてのバンド

「正しいストーンズ」という幻影
ローリング・ストーンズは、あまりにも長く、あまりにも中心に居続けたがゆえに、「正しい姿」が存在するかのように語られてきたバンドである。『ベガーズ・バンケット』『レット・イット・ブリード』『スティッキー・フィンガーズ』『メイン・ストリートのならず者』へと連なる時期が神話化され、その以後は下降線として処理される。だがこの語りは、あまりにも整理が良すぎる。
ストーンズは成立の瞬間から、純粋なブルース・バンドではなかった。彼らが行っていたのは、ブルース、ゴスペル、R&B、カントリー、ロックンロールといった黒人音楽を中心とする複数の文法を混成し、それを「ストーンズの音」として成立させる行為だった。その混成が結果的に正統化され、「これが本物のストーンズだ」と固定化されたとき、バンドは最初の危機を迎える。固定化とは、消費可能な形式への転落でもある。
ミック・ジャガーは、その危険を理屈ではなく嗅覚で察知していたように見える。彼が恐れていたのは失敗ではなく、成功の様式が凍結することだった。ストーンズの歴史は、成功をいかに裏切り続けるかの試行錯誤として読むことができる。

『エモーショナル・レスキュー』という踏み絵
1980年に発表された『エモーショナル・レスキュー』は、ストーンズのカタログの中でも特に評価が割れる作品である。ディスコ的、軽薄、流行迎合といった否定的言説が並ぶ一方で、その違和感こそが重要だとする見方も根強い。このアルバムが行っているのは、ストーンズ的価値の一時的停止である。
象徴的なのが、ミック・ジャガーのファルセットだ。ここでの声は、ブルース的な地声でも、ロック的な「本音の表出」でもない。むしろ、信用できない仮面として響く。歌が身体の真実を語るというロックの神話は、ここで意図的に裏切られている。
重要なのは、このファルセットが技術的完成を目指していない点である。美しくも、自然でもない。そのぎこちなさ自体が、「正しいストーンズ」という像を解体するための装置として機能している。『エモーショナル・レスキュー』は迷走ではなく、価値の踏み絵だった。どこまでをストーンズとして許容できるのか、その問いをリスナーに突きつけた作品なのである。

プリンスという同時代的反射
このファルセットを同時代の文脈で捉え直すとき、プリンスの存在は無視できない。1978年にデビューしたプリンスは、当初「誰なのかわからない存在」だった。性別も年齢も、ジャンルも曖昧で、ファルセットを多用しながら地声をほとんど見せない。その姿勢は、既存のロック的主体像と大きく異なっていた。
だがプリンスのファルセットは、突然変異ではない。フィラデルフィア・ソウルやアース・ウィンド&ファイアー、カーティス・メイフィールドに連なる、黒人音楽における長いファルセット文化の延長線上にある。ただし彼はそれを「本質の声」としてではなく、徹底的に演技化し、個人のキャラクターとして結晶化させた。
ミック・ジャガーが反応したのは、プリンス個人というより、ファルセットが再び前景化する文化状況だったと考えられる。ディスコ以後の軽量化された身体、性の曖昧化、声の仮面化。その流れは、ロックの重心を下げ、真実性の神話を相対化する力を持っていた。ミックはそこに、ストーンズを固定化から救い出す可能性を嗅ぎ取った。
プリンスがファルセットを「本体」としたのに対し、ミックはそれを「異物」として導入した。この違いは決定的だが、共通しているのは、声をアイデンティティの証明にしなかった点である。声は可変であり、戦略であり、編集可能な素材であるという理解が、両者には共有されている。
編集としての創造 ― テオ・マセロ的思考
ストーンズが長く生き延びた理由の一つは、創造を内部完結させなかった点にある。彼らはプロデューサーを固定せず、その時代の旬を外部から取り込み続けた。仕上げを外注すること、創造をストレージ化することが、ストーンズの文化として定着していく。
この姿勢は、マイルス・デイヴィスとテオ・マセロの関係を想起させる。マセロは録音素材を編集し、時間を切断し、再構成することで作品を成立させた。創造とは演奏の瞬間ではなく、編集の過程に宿る。その考え方は、ロックにおける「バンドの自然な一体感」という神話とは対極にある。
ビル・ワイマン脱退後にダリル・ジョーンズが起用された際、「マイルスとやっていたやつだ」という発言が象徴的に語られるのも偶然ではない。ダリル以後のストーンズが、ワイマン的役割を再現しなかったのは、欠落ではなく更新だった。ヴードゥー・ラウンジ以後のサウンドは、編集されたストーンズ、再定義されたストーンズの姿である。
完成を拒否する完成形 ― 混成の倫理としてのストーンズ
『スティール・ホイールズ』は、しばしば「復活作」と呼ばれる。しかしこの言葉は正確ではない。そこにあるのは、失われた何かの回復ではなく、むしろ一度解体された価値が、別の形で再編成された姿である。捨て曲のない構成、過剰なまでのエネルギー、バンドとしての機能美。そのすべては確かに完成形と呼びうる説得力を持っているが、それは神話的な完成ではない。
このアルバムが成立した前提には、『エモーショナル・レスキュー』という危険な工程があった。そこで行われたのは、ストーンズ的正しさの一時停止であり、声の仮面化であり、価値の宙吊りである。ファルセットという異物を導入し、ブルース的本物性を裏切り、ロックの倫理を疑問に付す。その過程を経たからこそ、『スティール・ホイールズ』は単なる保守的回帰ではなく、更新された強度を獲得することができた。
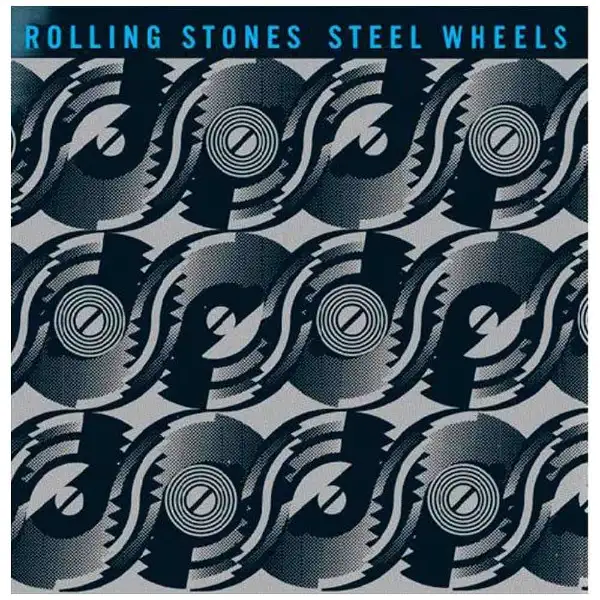
この一連の振る舞いは、純粋性を目指す近代的な美学とは異なる方向を向いている。混ざり合い、過剰を抱え込み、少し居心地の悪さを残したまま成立してしまう構造。それは、完成度の高さと同時に、どこか胡散臭さを失わない状態でもある。ストーンズが長く生き延びた理由は、まさにこの「いかがわしさ」を推進力として保持し続けた点にある。
比喩的に言えば、それはドライカレーにとんかつが別皿で添えられているような状態に近い。どちらか一方を純化させれば整うが、あえて混在させることで、過剰な満足感と余剰が生まれる。この余剰は、洗練とは別のかたちでの持続可能性を生む。ストーンズの混成は、常にこの余剰を失わないための実践だった。
カツカレーカルチャリズムという言葉を用いるならば、ストーンズは最初からその倫理を体現していたと言えるだろう。ブルースでありながらブルースに回収されず、ロックでありながらロックの正統性に安住しない。編集を恐れず、外部を導入し、声さえも仮のものとして扱う。そのすべてが、固定化=消費への抵抗として機能してきた。
ストーンズに「正しい姿」は存在しなかった。存在したのは、常に暫定的で、更新可能な形だけである。『エモーショナル・レスキュー』はその事実を最も露骨に示した作品であり、『スティール・ホイールズ』は、その危険を引き受けた後にのみ到達しえた地点だった。彼らの到達点とは、完成そのものではなく、完成を一度疑い、なおかつ成立させることができた、その倫理の強度にあったのではないだろうか。




コメント