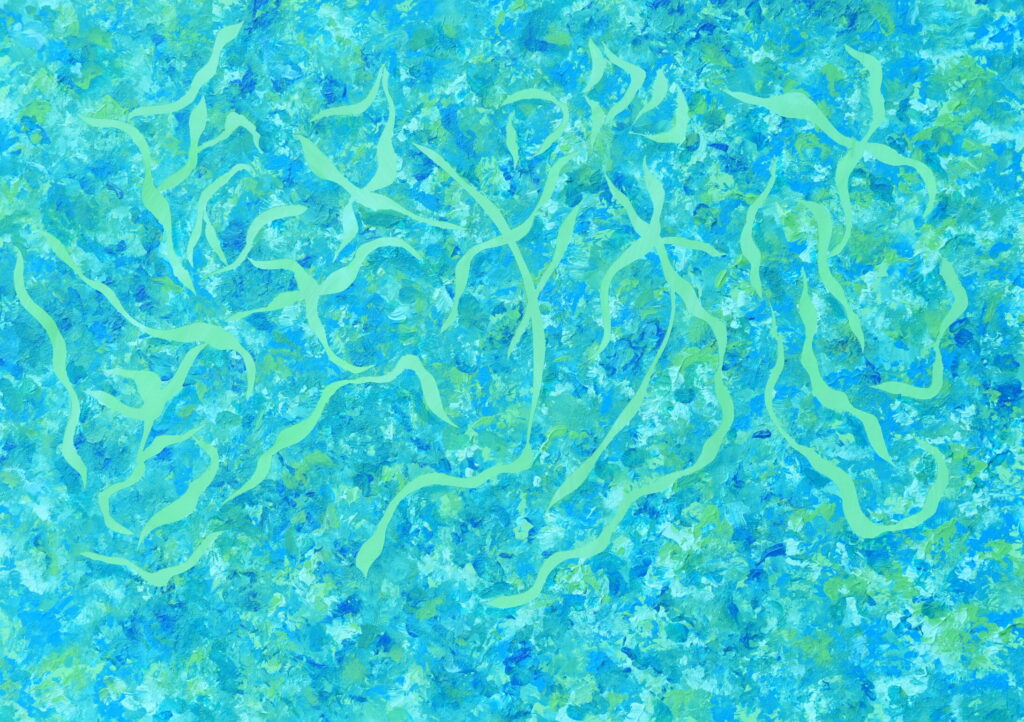
同じ皿に盛るという態度
「没入」と「メタ」をどう両立させるかという問いは、現代の制作において繰り返し立ち上がってきた。没入は身体の速度や快を生み、メタは構造の理解や距離を与える。多くの表現は、この二つを時間的に分離して処理する。制作中は没入し、後から言葉や理論で回収する。しかし、この分離そのものが、作品の呼吸を止めてしまう場面も少なくない。
ここで提案したいのが、没入とメタを分けず、しかし混ぜ切らず、最初から同じ皿に盛るという態度である。比喩としてのカツカレーは、この感覚を身体的に理解させる。そこでは、わかる前に噛むこと、噛みながらわかってしまうこと、その両方が同時に起きている。
噛むことから始まる制作
制作の最初の一口は、説明を拒否する。揚げたてのカツを噛むとき、理由や意義は後回しになる。音、温度、抵抗が先に立ち、身体が主導権を握る。この段階で重要なのは、衝動を神話化しないことだ。勢いに身を任せながらも、それを絶対化しない。認知よりも先に身体が反応する瞬間を、制作のエンジンとして信じるが、最終目的にはしない。
カツに少しだけカレーを浸すと、触感は保たれたまま、味の層が増える。この「少し」に制作の倫理が宿る。メタは後付けの解説ではなく、味として内部に染み込む。ここで起きているのは、俯瞰ではなく内在である。噛んでいる最中に、構造が舌に触れる。この内在的メタが、没入を壊さず、しかし盲目的にもさせない。
白米は、制作における沈殿の層である。派手さも主張もないが、口内を整え、次の一口を可能にする。意味や物語を提示しない時間、ただ在る配置や弱い部分が、作品を一度で終わらせない。未回収のまま沈殿する層があることで、体験は持続し、再訪を要求する。
この制作は直線的な手順ではない。噛み、浸し、休み、また噛むという往復が続く。最初と二度目では、同じ一口でも味が違う。時間が介入することで、身体の感度が更新される。この循環がある限り、制作は揚げたての瞬間に閉じない。
外部としての異物 ─ 福神漬けとらっきょう
カツカレーの皿には、主役ではない存在が置かれている。福神漬けは、口内の地図を一瞬で書き換える異物である。制作においてそれは、偶然のノイズ、誤読、意図しない引用、空間の癖といった外部性にあたる。重要なのは、これらを意味やコンセプトとして回収しないことだ。説明せずに効く異物を残す勇気が、作品を閉じさせない。
一方、らっきょうは意図された休符である。酸味は明確で、食べるタイミングは選択できる。制作における余白や間、弱い一点は、体験をリセットし、次の噛みを可能にする設計だ。ただし、制御された休符は外部そのものではない。福神漬けと混同すると、世界は過度に安全になり、予測不能性を失う。
YBAとハースト ─ すべてが盛られた皿の先へ
1990年代以降の英国、とりわけYBAに象徴される表現は、同時代の音楽やメディア環境と強く共振しながら、強烈な即効性を獲得した。ダミアン・ハーストの作品群は、死や消費、制度といった主題を、誰にでもわかる形で一挙に提示する。そこでは皿そのもの、盛り付けの仕方、提示の強度が作品の中心に置かれている。

この戦略は否定されるべきものではない。むしろ、没入とメタを最初から同時に可視化した点で、極めて誠実でもあった。ただし、その多くは最初からすべてがカレーに浸った状態に近い。意味も構造も衝撃も、一口で提示される。その結果、理解は早く、体験は強いが、噛む時間は短くなる。温度が下がったとき、何が残るのかという問いが立ち上がる。
カツカレー的制作は、ここから先に進もうとする態度である。盛り付けの強度やプロデュースの技術を引き受けつつ、それだけに回収されない噛みどころを内部に残す。皿を見る前に噛ませ、噛んだ後で初めて構造に気づかせる。その順序を手放さないことで、神話化やイメージの膨張を乗り越え、時間に耐える体験へと向かう。
冷めても噛めるということ
冷めるとは、初見の衝撃や時代性の温度が剥がれることである。多くの作品は、冷えると噛めなくなる。だが、意味ではなく構造が残っていれば、身体は仕事を続ける。配置、間、スケール、抵抗。これらが効き続ける限り、再訪のたびに異なる噛みが起きる。
冷めても噛める表現は、派手ではない。最初はわかりにくいことさえある。しかし、快が消えたあとに身体の仕事が始まる。時間を引き受ける構造を持つことで、制作は一回性を超える。
責任を取るメタ ─ 結びにかえて
没入とメタを同じ皿に盛るとは、逃げ場を作らないということだ。本気で噛ませ、同時にわかっているという態度を、言葉ではなく身体に仕込む。アイロニーを防衛に使わず、外部を回収せず、冷えを引き受ける。 カツカレーカルチャリズム的制作の倫理は、下品さや雑味を恐れない代わりに、時間への責任を引き受ける倫理である。噛むことをやめない限り、制作は終わらない。
結語 ― 判断を引き受けるということ
制作の現場で起きている最も重要な出来事は、しばしば作品の外からは見えない。それは成果としてのイメージでも、語りうるコンセプトでもなく、むしろ「判断を引き受け続けた時間」そのものである。ゾーンと呼ばれる状態は、その時間が最も純度の高いかたちで立ち上がる局面にほかならない。
そこで作家は、何かを表現しているという自覚すら失いながら、それでも無数の微細な判断を行っている。「ちがう、そうじゃない」という言葉にならない否定と、「こういう感じ」という方向感覚。その反復が、結果として作品の形を導く。しかし重要なのは、その判断が正しかったかどうかではない。判断の理由を他者や理論に委ねず、自分の身体と時間の中で引き受けたかどうかである。
YBAやハースト以後、表現はきわめて可視的で、即時的で、説明可能なものになった。それは一つの達成であり、同時に誘惑でもあった。強度や明快さを前景化することで、判断の所在が曖昧になり、制作がプロデュースや神話に回収されていく危険も生じた。カツカレーカルチャリズム的制作倫理は、そうした状況を否定するのではなく、そこを通過したうえで、もう一度制作の内部に判断を引き戻そうとする態度である。
揚げたてのカツのような即効性も、冷めたあとに噛みしめられる持続性も、そのどちらか一方では足りない。没入とメタ、快楽と距離、信頼と疑念を同じ皿に盛り、その都度の噛みごたえを引き受けること。その反復の中でのみ、表現は時間に耐える。
カツカレーカルチャリズム的制作の倫理とは、正しさを保証する原理ではない。それは、制作しているその時間を裏切らないという態度であり、ゾーンの中で起きた判断から逃げないという約束である。冷めても噛める表現とは、結果としてそうした時間を通過してきた痕跡にほかならない。




コメント